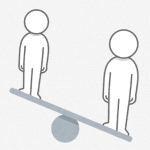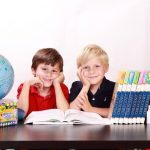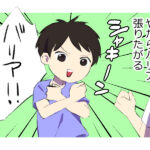ランドセルのデザインや機能は、時代によって少しずつ変化しています。カラーを例に挙げても、昔は赤と黒の2色しかなかったのに、現在では数十色ものカラフルなランドセルから選べる時代になりました。
ランドセルが一般の人に普及し始めたのは、高度経済成長期の1960年代頃といわれます。それから半世紀以上、ランドセルのデザインやカラー、素材、価格などは、どのように変化してきたのでしょうか。その歴史をひも解いてみましょう。
1960年代のランドセル
1960年代といえば、高度経済成長時代。おじいちゃん・おばあちゃん世代がランドセルを背負って登下校していた時代ではないでしょうか。このころの物価は、サラリーマンの平均月給が2万円くらい。ランドセルの価格は2,500~3,600円だったそうです(※)。
当時のランドセルの素材は、牛革が流行し始めたころ。少し前の1950年代には、豚革、ブリキ製、紙製などのランドセルもありました。革製なかには、カブセに野球をモチーフにした絵や、鳥と花といった刺繍を施したランドセルもあったようです。
赤黒のランドセルが登場
今では定番となった「男の子が黒」「女の子が赤」のランドセルは、1950年代からあったようです。この2色になった理由は、諸説あります。
当時の染色技術は途上段階で、牛革にムラなく染められたのが赤と黒だったという説が有力です。このほか、「男の子と女の子を一目でわかりやすく見分けられるから」という説もあります。
ちなみに、さまざまなカラーバリエーションが展開できる人工皮革のクラリーノが開発されたのが1964年。1970年代からランドセルに使用されるようになりますが、クラリーノの色も当時は赤と黒しかありませんでした。
今よりコンパクトなランドセルが主流
1960年代のランドセルは、今よりサイズの小さい商品が多かったようです。教科書や学校で配られるプリント類は、B5サイズが主流だったためで、それが入る大きさが一般的だったのです。マチ幅も現在の半分ほどしかなく、容量が小さかったことがわかります。
牛革などの天然皮革は強くて丈夫という特徴がありますが、当時のランドセルはそれほど強くなかったようです。たとえば、肩ベルトは現在より細く、背カンと直接固定してある商品が多くみられます。強く引っ張ると、ベルトがちぎれそうな商品もあったと想定されます。
また、背あてはアルミに布を貼付けただけというランドセルもあり、長時間背負っていると背中が痛くなった子も多かったかもしれません。アルミは背あてのほか、ヘリの部分にも使われている商品がありました。ぶつけても傷つかない工夫だったと思いますが、体に当たると痛みを感じるでしょうし、全体重量が重くなってしまう一因にもなっていたようです。
1980~90年代のランドセル
「一億総中流」といわれ、多くの日本人が裕福になった1980年代。現在のお父さん・お母さんが小学校に入るころのランドセルは、インフレによる高騰が続いていました。
1982年の平均価格は約1万8,000円だったのが、2年後の1984年は2万2,000円、さらに1990年には3万3,000円と、わずか8年の間に2倍近くも上昇したようです。その後も上昇を続けますが、バブル崩壊によって経済が混とんとしてくると、ランドセルの価格は3万5,000円前後で推移するようになります。
素材は人工皮革が躍進してきましたが、当時の人工皮革は改良の余地が大きかった時代でしたから、牛革など天然皮革の人気が根強かったようです。
カラーやデザインに個性が現れる
この時代は、今のような「ラン活」がない時代。親や祖父母が買ったランドセルを子どもに与えるというのが、一般的でした。カラーは赤か黒が主流ですから、メーカーの違いはあっても、子どもが選択できるような違いはなかったのかもしれません。
ただ、この時代になると赤黒以外のオーダーメイドランドセルも登場していたようです。デザインも、半かぶせ型のようなランドセルがあったようですが、手間もコストもかかるためか、それほど普及しませんでした。
容量が大きくなる
ランドセルのサイズは、1960年代とほぼ同じ。B5サイズのプリント類が入る、今よりも一回り小さいものでした。ランドセル工業会がA4サイズを標準に定めたのは1998年。それまでは、B5サイズが一般的だったのです。
なお、教材が増えたこともあって大マチの幅が大きくなり、容量が増えてきたのは特筆すべきポイントでしょう。
ランドセルのバリエーションが増えた2000年代
バブル崩壊後の平成不況は、21世紀に入っても続きました。ランドセルの平均価格は3万5,000円前後で推移しますが、その後、デフレ時代に突入。2006年には2万9,900円まで下落します。ただし、ランドセルのデフレは長く続かず、2007年頃から3万円台を回復。その後も、平均価格は高騰していきます。
そんななか、ランドセル業界に大きな革新が起こります。2001年、イオンが24色ものランドセルを販売。赤黒以外のランドセルが、広く手に入るようになったのです。このころから、ランドセルを背負う子ども本人が選ぶことが重視され始めたのかもしれません。
デザインも、学習院型だけでなく半かぶせのタイプも普及し、選択肢が広がっていった時代といえます。
現代のランドセル
少子化によりランドセルの需要は減ってきていますが、ランドセルの価格は高騰を続けています。2014年の平均価格は4万2,400円と、初めて4万円を突破。その後も上昇を続け、2020年には5万3,600円になっています。
価格高騰の背景には、子ども一人にかけるお金に余裕が出てきたこと、本物志向の工房系やデザインに凝った高額ランドセルに人気が出てきたこと、原材料費の高騰などが影響を与えているようです。
一方で、量販店では低額のランドセルも増えており、価格的にも選択の幅が広がってきたともいえるでしょう。
ランドセルの大型化が進む
2011年、小学校では新学習指導要領のもと、脱ゆとり教育がスタートします。教科書やプリント類は大きくなってA4サイズが主流に。それに伴い、ランドセルも大型化していったのです。
その一方で、ランドセルの軽量化がメーカーの課題になってきます。メーカーでは、新しい人工皮革やパーツの採用などによって、より軽く、より丈夫で、より長持ちするランドセルの開発がいまも続けられています。
まとめ
ランドセルのデザインやサイズは、時代によって少しずつ変化してきたことが、おわかりいただけたのではないでしょうか。
それは、単なる流行による変化だけでなく、その時代の教育事情に合わせたり、利用者の声を反映したりしながら、より使いやすい商品づくりを追求してきたランドセルメーカーの努力でもあります。
これからも、さまざまなランドセルが登場し、選択肢はさらに広がるかもしれませんね。